
|
 |
2015(平成27)年『大乗』10月号「みほとけとともに」 |
西本願寺より発行される月刊誌『大乗』の「みほとけとともに」コーナー、第三弾です。後輩から、大乗に掲載されている私の「写真の顔が怖い」という指摘を受けました。私が見るに、そんなに怖いとは思わないのですが、日頃、いろんな所でほえているからなのか、噛みついているからなのか。私の生き様がそう見せたのは、間違いないところです。
|
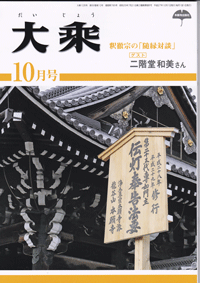
|
近頃の葬儀はほとんどが葬儀会館で行われるようですが、私の住んでいる地域では、いまだに自宅葬や、家から出棺しお寺で葬儀を営む形が中心です。
自宅の葬儀は大変です。お客さんに気も使うし、準備から片づけまで大忙し。何より休む場所がありません。一方、会館の葬儀は気配りも行き届き、サービスも充実。何より家に帰れば一息つけます。
誰もが楽な方を選びたい思いはありますが、流されることで見えなくなることもあるはずです。葬儀社さんの悪口を言うつもりはないのですよ。それぞれのご事情もあるでしょうから、会館での葬儀を否定するつもりもありません。しかし簡略化に流されて、「人間一人が死ぬとは、こんなに大変な事なのか」と身体を通して受けとめる経験を失うと、一人の人間が生きてきた事実の重さも見失われていくように思うのです。
死を悼むことを簡略化するほどに、一人の人生を、大切な人を失った悲しみを、軽く扱うようになります。私の知人は「おじいちゃん、おばあちゃんが死んだくらいでは、会社は休めませんから」と言われたそうですし、赴任先でお母さんが亡くなったことを上司に伝えると「それで、どうしますか?帰りますか?」と真顔でたずねられ、「母親が死んで、帰らない息子がいるんですか?」と叫んだというご門徒もありました。いのちを軽く扱うとは、簡単に踏みにじることができるということでもあるのです。
何年も前になりますが、私の祖母の葬儀が済み初七日の法要を終えた頃、近所の方から「次第次第に、お寂しくなりますね。」という言葉をかけられ感動したことがありました。葬儀の慌ただしさが一段落してホッとしたと同時に、しみじみと別の形で悲しみが味わわれてくる。そんな心境に配慮した言葉が、挨拶になって定着していることに驚いたのです。ところが今や「いつまで引きずっている」「早く切り替えて、前向きに」という声はあっても、悲しみを尊重できなくなってはいないでしょうか。
精神医学・精神分析の基礎を築いたフロイトは、「悲哀の仕事」ということを言っています。大切な人を失った悲しみを、きちんと悲しむことができないと、人間は精神に支障をきたすのだと。それはそうでしょう。大切な人だから、悲しいのです。大切でなかったら、悲しくはありません。大切な人を大切に思えなくなっているということは、既に支障をきたしているということでしょう。作家の柳田邦男さんは「悲しみの感情や涙は、実は心を耕し、他者への理解を深め」るものだと言われています。悲しみを通すからこそ、見える世界があるのだと。悲しみには大切な仕事があるのです。
「悲」とは「非」と「心」という字でできた漢字ですが、「非」は鳥が翼を広げ両方から引き裂かれていることをあらわします。古代インドのサンスクリット語では「悲」をカルナー(うめき声)といいますから、「悲しみ」とは、大切な人がいたという事実と、その人を失った事実との間に引き裂かれ、うめいている姿ということです。つまり、悲しみが深いほど大切に思う心も深いということなのでしょう。悲しむ姿は大切に思う姿です。ということは、何を悲しむのかが、その人が何を大切にしているのかを明らかにするということだと教えられるのです。
かつて大谷大学で教鞭をとられた藤本正樹先生は「今の大学には、対策はあるけれども悲しみがない。」と言われたそうです。政治の世界でも、教育現場でも、どこでもさまざまな問題が起こる。それに対して、対策を講じなくてはならない。時には、問題を起こした学生を見放さざるをえない場合もある。人間ですから、何もかもうまくはできません。しかし、そこに深い「悲しみ」があるのかどうか。簡単に、事務的に「しかたがない」と切り捨てて安心してはいないか。その悲しみの心が、傷みが、相手の存在を大切に思う気持ちであると。その心が見失われたとき、そこにあるいのちは軽く扱われ、処理されていくと藤本先生は指摘されるのです。
仏法を学ぶとは、「仏の大悲心を学ぶ」(帰三宝偈)ことだと善導大師は言われます。つまり、阿弥陀様が何を悲しみ、何を大切にしているのかを学ぶということなのでしょう。阿弥陀様から見れば、悲しむべきことを悲しめず、大切なことを大切にできずにいる私たち。その有り様に深い悲しみを持ちながら、決して捨てることなく、どこまでも共に生きていこうと願い続けて下さっている心。この阿弥陀様の深い悲しみを「如来の大悲」というのだと教えられるのです。そんな阿弥陀様の悲しみを深くいただくこともなく生きていることを、せめて悲しむところから始めなくてはなりません。■
|

|
  |