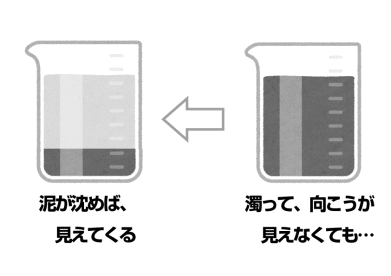|
|||
|
2021(令和3)年7月 |
|||
真宗大谷派の僧侶・宮城顗先生は、「人間は欲深いというが、幸せを独り占めにしたいと同時に、悲しみさえも独り占めしたいものなのだ」と教えてくださいました。「幸せを独り占めにしたい」という思いはわからなくはありません。では「悲しみを独り占めにしたい」とは、どういうことなのでしょうか。
東本願寺で開催された座談会に、宮城先生が講師として参加された時のお話です。座談会のメンバーは、東本願寺に参拝された人たち。様々なところから、年齢層もバラバラな方々が集まっておられます。
その中に、若い人たちのグループがありました。聞くと、グループの中心である女性の弟さんが、病気で亡くなられたのだそうです。その後、弟さんの「病気が治ったら、ああしたい。こうしたい」という思いが書かれたノートが出てきました。思いを果たすことなく亡くなった弟が、可哀想で仕方がない。代わりに私が果たしていこうと、その女性は思われたのです。そしてそのノートに「京都の東本願寺にお参りがしたい」と書かれていたのだと。病いの中で、浄土真宗関係の本を読まれたのでしょうか。彼女が、そのことを弟さんの友だちに話すと、「一緒に行きましょう」と言われ、今日参拝したということでした。
彼女は、「これが母親ならもう年も年だし、一応人生いろんな経験もしているから、順序からいっても悲しくてもまだあきらめがつくけれども、自分より若く、ほとんど人生経験もなしに死んでいった弟が哀れでしかたがない。弟を失った悲しみというのは、こんなに辛いものだとは思わなかった」と言われました。
すると、一人で参加しておられた女性が、「これが母親ならと、あなたはそう言われましたが、母を失った悲しみがあなたにわかるのですか。私は、先日母を亡くしました。母を失うことがこれほどつらいとは、思いませんでした。それで、どうにも生きる力が湧かなくて、本願寺にお参りしたのです。共に過ごす時間が長いほど、思い出も多く、悲しみもまた深いのです。あなたに母親を失った悲しみがわかるのですか」と怒り出されました。そこから座談会そっちのけで、「母親を失ったほうが悲しい」「いや、弟を失った方が悲しい」と言い争いになってしまったのだそうです。
大切な人を亡くす悲しみは、周りの者が評価できるようなものではありません。二人とも、深い悲しみの中におられるのでしょう。ところが二人はいつの間にか、「自分の悲しみの方が深い」と主張し始めてしまった。まさに、悲しみを奪いあい、独り占めしようとされたのです。宮城先生はその時、「人間は悲しみさえも独り占めしたいものなのだ」と思われると同時に、これは二人だけのことではなく、私たちがそれぞれに抱えている、人間の本質なのではないかと思われたそうです。
私たちは悲しみに出遭う時、「どうして私がこんな目に遭わなければならないのか」という思いに陥ります。そして「私が」という思いが強まると、いつしか「私だけが…」「私の思いが、あなたにわかってたまるものか…」という思いへと変わっていく。まさに、悲しみを独り占めしようとするのです。そのことが、形は違えど同じような悲しみに生きておられる人がいることを、見えなくさせてしまうのでしょう。
このような有り様を、宮城先生は「悲しみが濁る」と言われました。仏教では、煩悩を「濁り」に譬えます。透明のコップに濁った泥水を入れると、向こう側は見えなくなります。同じように、悲しみを「私だけが」という思いで濁らせてしまうと、周りが見えなくなり、ますます自分の思いに閉じこもることになってしまいます。
その濁りを照らし出し、新しい世界との出遇いを開かせてくださるのが、阿弥陀様のはたらきなのだと教えられるのです。濁った泥水も、落ち着くと泥が沈殿し、次第に水は透きとおり向こう側が見えてきます。同じように、阿弥陀様のはたらきに出遇い、立ち止まり、振り返り、落ち着くことで、自分の悲しみを通して、人間がそれぞれに等しく持つ悲しみに目覚めていく。「どうして私だけが」という独り占めの思いから、「形は違っても、あなたも同じような悲しみの中を生き抜いておられるのですね」という出遇いが広がっていく。そこに頷きがあり、お互いが尊ばれていく世界が開かれていく。「私の方が悲しい」という世界から、悲しみを共にしていく身に育てられていくのだと、宮城先生は示してくださったのです。
『阿弥陀経』に「五濁悪世」という言葉が、あります。「五濁」とは、煩悩に濁った世に生きる人々の、五つの相(劫濁・見濁・煩悩濁・衆生濁・命濁)を示されたものです。
「劫濁」とは、時代や社会の濁りということ。
最後の「命濁」とは、人の寿命が短くなるということです。それは、命の年数が短くなるということではありません。生きる喜びが見失われ、生きていることの有り難さが実感できなくなり、互いに尊重することもなく、命の豊かさが薄らいだ状態のことをいいます。(『和讃に学ぶ』宮城顗・『正信偈の教え』古田和弘) 私たちが生きる現代社会を、そのまま言い当てたような言葉ではないでしょうか。もちろん『阿弥陀経』は、約二千年前に書かれたお経ですから、この言葉は人間の世の本質をあらわしているのでしょう。しかし現代社会は、その濁りがますます深まっているように思われます。私たちはまさに、「濁世」を生きているのです。
近頃は、通りすがりの人々を傷つけ、時には死に至らしめる「無差別殺傷事件」が増えています。事件を起こした彼らは、共通して孤独感と疎外感を抱えていたようです。自分の居場所が見出せず、生きる喜び充実感も感じられない。そんな彼らの思いが、そのような形となって噴き出してしまったのかもしれません。 もちろん、事件を起こしたことを肯定するわけではありません。しかし、彼らの悲しみは彼らだけの責任だと、私には思えないのです。「自己責任」という言葉が独り歩きし、迷惑をかけてはいけないという思いに縛りつけられ、苦しみも自分一人で担わなくてはならないような時代です。いや、すべて個人に押しつけて、ケロッとしている時代と言っても良いのかもしれません。助けを呼ぶこともできず、悲しみを共感することさえ許されない。そんな濁りが社会を覆っています。 「濁世」を生きていることに気づき、悲しみを共にし、分かちあう世界に出遇う。そんな生き方に目覚めよと、阿弥陀様は私たちに呼びかけられているのです。だからこそ親鸞聖人は、阿弥陀様のはたらきを「濁世の目足」、煩悩に濁った世に生きる者の目となり足となるものだと、示されているのでしょう。奪いあい、独り占めにする生き方から、分けあい、共に生きる生き方へと歩み出したいものです。■
|
|||
 |